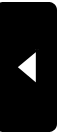スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2020年06月02日
【地域の史跡9】 日枝神社末社 天満神社
【地域の史跡9】 日枝神社末社 天満神社
場所:高山市森下町城山 日枝神社境内
祭神:菅原道真

日枝神社の境内にも学問の神様「菅原道真公」をお祀りした神社がある。
明治25年3月5日に上木小三郎が私財を当日菅公廟を改築した記録がある。
その後大正15年(1926)7月に天満神社を公園内に移転造営した。これが現在の高椅神社社殿である。
昭和62年に稲荷神社が新築されたのに伴い、旧稲荷神社の社祠を社殿としたのが、現在の天満神社である。
構造は流造りで前面に大唐破風が施され、本殿、幣殿、拝殿を合わせ一つの建物となっている。
参考文献:『日枝神社史』
K.N.
場所:高山市森下町城山 日枝神社境内
祭神:菅原道真
日枝神社の境内にも学問の神様「菅原道真公」をお祀りした神社がある。
明治25年3月5日に上木小三郎が私財を当日菅公廟を改築した記録がある。
その後大正15年(1926)7月に天満神社を公園内に移転造営した。これが現在の高椅神社社殿である。
昭和62年に稲荷神社が新築されたのに伴い、旧稲荷神社の社祠を社殿としたのが、現在の天満神社である。
構造は流造りで前面に大唐破風が施され、本殿、幣殿、拝殿を合わせ一つの建物となっている。
参考文献:『日枝神社史』
K.N.
2020年06月01日
【地域の史跡8】 日枝神社の大杉
【地域の史跡8】 日枝神社の大杉
場所:高山市森下町城山 日枝神社本殿前
種類:スギ
樹齢:1000年

日枝神社の大杉は推定樹齢1000年、目通り約7m、高さ約39mである。神明神社の大杉は推定樹齢300年以上、目通り約m、高さ約36mである。
参考文献:『日枝神社史』
K.N.
場所:高山市森下町城山 日枝神社本殿前
種類:スギ
樹齢:1000年

日枝神社の大杉は推定樹齢1000年、目通り約7m、高さ約39mである。神明神社の大杉は推定樹齢300年以上、目通り約m、高さ約36mである。
参考文献:『日枝神社史』
K.N.
2020年05月31日
【地域の史跡7】 上山王宮 日枝神社跡 (片野町公園)
【地域の史跡7】 上山王宮 日枝神社跡 (片野町公園)

上山王宮の由緒として、地元の敬神会の作成した看板には次のような記述となっている。
「上山王宮由緒 白弊社 高山市片野町五丁目一番地
上山王宮秋葉神社は慶長十年(1605)高山城主となった金森長近が、当時片野村の産土神であった山王宮を城の守護神とするため、
杉ヶ平から現在の日枝神社鎮座地へ奉遷した。
そのため村人たちは永年崇敬してきた産土神である山王宮の御分霊をこの場所に奉安し、上山王宮と称し九月二十六日を例祭日と定めた。
そしてたまたま当社社殿の傍らに勝久寺の説教所の御堂があった事から誰いうとなく人々は堂の前(どうのま)神社、あるいは堂の前祭り
などと言うようになった。
時移り人変わり明治三年全国的に神社登録が行われた際、日枝神社神職であった松樹鍋友は何故か秋葉神社として報告した。
しかしこの報告以前に当社を秋葉神社とする資料は見当たらない。蓋し幾多の紆余曲折や有為転変に遭遇しながらも四百余年にわたって
神社は常に片野住民の慎警と融和の心に支えられ、守り継がれて現在に至っている。
尚、昭和45年以降は例祭日を毎年九月第三日曜頃としている。
平成十年七月佳日 片野町敬神会建之」

なお、この公園には、大原騒動で殉死した片野村民の慰霊碑もある。
参考文献:「上山王宮敬神会 看板」
K.N.
上山王宮の由緒として、地元の敬神会の作成した看板には次のような記述となっている。
「上山王宮由緒 白弊社 高山市片野町五丁目一番地
上山王宮秋葉神社は慶長十年(1605)高山城主となった金森長近が、当時片野村の産土神であった山王宮を城の守護神とするため、
杉ヶ平から現在の日枝神社鎮座地へ奉遷した。
そのため村人たちは永年崇敬してきた産土神である山王宮の御分霊をこの場所に奉安し、上山王宮と称し九月二十六日を例祭日と定めた。
そしてたまたま当社社殿の傍らに勝久寺の説教所の御堂があった事から誰いうとなく人々は堂の前(どうのま)神社、あるいは堂の前祭り
などと言うようになった。
時移り人変わり明治三年全国的に神社登録が行われた際、日枝神社神職であった松樹鍋友は何故か秋葉神社として報告した。
しかしこの報告以前に当社を秋葉神社とする資料は見当たらない。蓋し幾多の紆余曲折や有為転変に遭遇しながらも四百余年にわたって
神社は常に片野住民の慎警と融和の心に支えられ、守り継がれて現在に至っている。
尚、昭和45年以降は例祭日を毎年九月第三日曜頃としている。
平成十年七月佳日 片野町敬神会建之」

なお、この公園には、大原騒動で殉死した片野村民の慰霊碑もある。
参考文献:「上山王宮敬神会 看板」
K.N.
2020年05月30日
【地域の史跡6】 舊山王宮跡 昔の日枝神社
【地域の史跡6】 舊山王宮跡 昔の日枝神社

『日枝神社史』によれば、平清輔朝臣によって城の鎮護神として祀られていた「日吉神」はその後、片野の里人の産土神として祀られていた。その場所は、飛び地としての社有地で、日枝神社が現在地に奉遷されるまで鎮座したばしょであった。このちは往年二之町村に住んでいた
大坂屋太右衛門所有の地で、万延元年(1860)12月に自分の持山分に併せ、隣接地を購入して日枝神社に寄進した。
その杉ヶ平の周辺部1町四反12歩となっている。近年は地元の敬神会によって碑が建てられ、「元山王跡」として後世に伝えられていたが、平成29年現在この碑はどこにも見当たらず地元の人も御存じなかったが、今でも山林の中に石碑が存在している。

この場所では、例大祭の時に旗が建てられることになっており、普段は木を三又に組んだ旗台がある。
参考文献:『日枝神社史』
K.N.
『日枝神社史』によれば、平清輔朝臣によって城の鎮護神として祀られていた「日吉神」はその後、片野の里人の産土神として祀られていた。その場所は、飛び地としての社有地で、日枝神社が現在地に奉遷されるまで鎮座したばしょであった。このちは往年二之町村に住んでいた
大坂屋太右衛門所有の地で、万延元年(1860)12月に自分の持山分に併せ、隣接地を購入して日枝神社に寄進した。
その杉ヶ平の周辺部1町四反12歩となっている。近年は地元の敬神会によって碑が建てられ、「元山王跡」として後世に伝えられていたが、平成29年現在この碑はどこにも見当たらず地元の人も御存じなかったが、今でも山林の中に石碑が存在している。

この場所では、例大祭の時に旗が建てられることになっており、普段は木を三又に組んだ旗台がある。
参考文献:『日枝神社史』
K.N.
2020年05月29日
【地域の史跡5】昔の日枝神社
【地域の史跡5】 昔の日枝神社について1 石光山


そもそも日枝神社は、平安時代に平清輔朝臣が石光山に上がった時に紫雲がたなびき、白猿に出会ったことから、
吉兆の兆しであるとして、日枝神社を勧請したことに始まる。
今でも石浦町の石光山には、日枝神社古社跡の木柱が建てられ、地元の人によって管理されている。
K.N.

そもそも日枝神社は、平安時代に平清輔朝臣が石光山に上がった時に紫雲がたなびき、白猿に出会ったことから、
吉兆の兆しであるとして、日枝神社を勧請したことに始まる。
今でも石浦町の石光山には、日枝神社古社跡の木柱が建てられ、地元の人によって管理されている。
K.N.
2020年05月21日
【地域の史跡4】 和合神社
【地域の史跡4】 和合神社

所在地: 高山市森下町2丁目
祭 神: 和合神
森下町の信仰を集めているお社。一般の道祖神であるが、このお社にある和合神は蓮弁の上に並び立つ形で、外側の手を前で握り合い、内側の手はお互いに肩を抱き合う感じになっている。この和合神がいつ頃この場所に置かれたか伝承が全くない。この和合神社に因んで、宮川に掛けられた橋は「和合橋」という名称がつけられている。
神社前の看板には飛騨の匠の千鳥格子について書かれている。飛騨の匠は千鳥格子を得意とし、飛騨各所に匠の技を残している。
事務局KN
所在地: 高山市森下町2丁目
祭 神: 和合神
森下町の信仰を集めているお社。一般の道祖神であるが、このお社にある和合神は蓮弁の上に並び立つ形で、外側の手を前で握り合い、内側の手はお互いに肩を抱き合う感じになっている。この和合神がいつ頃この場所に置かれたか伝承が全くない。この和合神社に因んで、宮川に掛けられた橋は「和合橋」という名称がつけられている。
神社前の看板には飛騨の匠の千鳥格子について書かれている。飛騨の匠は千鳥格子を得意とし、飛騨各所に匠の技を残している。
事務局KN
2020年05月20日
【地域の史跡3】 富士神社
【地域の史跡3】 富士神社

所在地: 高山市森下町2丁目156番地 日枝神社本殿横
祭 神: 木花之開耶姫命
大物主神・白峰大神を祭神とする金刀比羅神社、
事代主命を祭神とする衣毘須神社の三社
建 物: 寛延元年(1748)創建 高山市有形文化財
大 工: 松田太右衛門
昭和10年6月、豪雨のため日枝神社の本殿の裏山が崩壊し、土砂や倒木のため、本殿が倒壊した。9月には日災によって、現在の富士神社の地に並んでいた末社5社(産霊神社、富士神社、金刀比羅神社、稲荷神社、衣毘須神社)が覆堂ととも消失した。その後、倒壊した日枝神社の本殿を修理し、富士神社として再建された。
この建物は、寛延元年(1748)に飛騨の名工 松田太右衛門によって建立されたもので、市内でも数少ない作品の1つである。
事務局KN

所在地: 高山市森下町2丁目156番地 日枝神社本殿横
祭 神: 木花之開耶姫命
大物主神・白峰大神を祭神とする金刀比羅神社、
事代主命を祭神とする衣毘須神社の三社
建 物: 寛延元年(1748)創建 高山市有形文化財
大 工: 松田太右衛門
昭和10年6月、豪雨のため日枝神社の本殿の裏山が崩壊し、土砂や倒木のため、本殿が倒壊した。9月には日災によって、現在の富士神社の地に並んでいた末社5社(産霊神社、富士神社、金刀比羅神社、稲荷神社、衣毘須神社)が覆堂ととも消失した。その後、倒壊した日枝神社の本殿を修理し、富士神社として再建された。
この建物は、寛延元年(1748)に飛騨の名工 松田太右衛門によって建立されたもので、市内でも数少ない作品の1つである。
事務局KN
2020年05月19日
【地域の史跡2】 「氷菓」の舞台になった日枝神社
【地域の史跡2】 「氷菓」の舞台 日枝神社
アニメで有名になった「氷菓」は、高山市が舞台となって作成されました。
その「聖地」の1つが、この山王地区にあります。
それは、「日枝神社」です。

日枝神社の大鳥居、土蔵が「聖地」として使われています。
荒楠神社(日枝神社) 【オープニング・20話】
荒楠神社のモデルである日枝神社の例祭は、春の高山祭と言われ、毎年4月14日・15日に開催されます。祭りには豪華絢爛な祭屋台の曳き揃えや、からくり奉納などが行われ、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。
住 所:岐阜県高山市城山156(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
アニメ画像:日枝神社写真

:日枝神社
 TVアニメ「氷菓」オフィシャルサイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
TVアニメ「氷菓」オフィシャルサイト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
 高山「氷菓」応援委員会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
高山「氷菓」応援委員会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
 高山「氷菓」応援委員会 Twitter(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
高山「氷菓」応援委員会 Twitter(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
アニメで有名になった「氷菓」は、高山市が舞台となって作成されました。
その「聖地」の1つが、この山王地区にあります。
それは、「日枝神社」です。
日枝神社の大鳥居、土蔵が「聖地」として使われています。
荒楠神社(日枝神社) 【オープニング・20話】
荒楠神社のモデルである日枝神社の例祭は、春の高山祭と言われ、毎年4月14日・15日に開催されます。祭りには豪華絢爛な祭屋台の曳き揃えや、からくり奉納などが行われ、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。
住 所:岐阜県高山市城山156(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
アニメ画像:日枝神社写真


:日枝神社
2020年05月19日
【地域の史跡1 日枝神社】
【地域の史跡1】 日枝神社の巻

山王地区まちづくり協議会の名前の元になっている「山王」とは、「山王様」いわゆる「日枝神社」が
地区内に在ることにあります。
高山市の森下町に日枝神社はあります。
所在地: 高山市城山156番地
社 格: 金幣社
主 神: 大山咋(くい)大神
例 祭: 4月14日(試楽祭) 4月15日(本楽祭)
由 緒: 永冶元年(1141)飛騨守、平時(たいらとき)輔(すけ)朝(あそん)臣が、あるとき狩に出て老猿に会い、よき獲物とばかりにこれを射た。獲物は見当たらず、矢は大杉に深くつき立っていた。 時輔は「大山咋神のお使いである老猿を救われたものである」とその神威を感じ、早速片野の石光山(しゃっこうさん)に城砦の鎮護神として、近江より日吉大神を勧請したのが、その始まりとされる。
四代景家の養和元年(1181)木曽義仲の手勢手塚太郎光盛に攻められて落城、社殿も兵火にあったが、幸いにも片野の里人に守られ、杉ヶ平、元山王に奉遷(ほうせん)され産土(うぶすな)神として奉祀された。その後、歳月は流れて天正13年(1585)織田豊臣時代に秀吉の臣、金森長近が飛騨に入国し、国内統一を果して国守に封ぜられた。 そこで城山に築城するに当たり、金森氏が代々守護神として崇めていた日吉大神を慶長10年(1605)に至り、片野より現在の地へ奉遷して城の鎮守神とした。 『飛騨の神社』
末社に富士社・金刀比羅社・稲荷社・恵比寿社・産霊社、天満社・杉ヶ谷神明神社がある。
事務局 KN
山王地区まちづくり協議会の名前の元になっている「山王」とは、「山王様」いわゆる「日枝神社」が
地区内に在ることにあります。
高山市の森下町に日枝神社はあります。
所在地: 高山市城山156番地
社 格: 金幣社
主 神: 大山咋(くい)大神
例 祭: 4月14日(試楽祭) 4月15日(本楽祭)
由 緒: 永冶元年(1141)飛騨守、平時(たいらとき)輔(すけ)朝(あそん)臣が、あるとき狩に出て老猿に会い、よき獲物とばかりにこれを射た。獲物は見当たらず、矢は大杉に深くつき立っていた。 時輔は「大山咋神のお使いである老猿を救われたものである」とその神威を感じ、早速片野の石光山(しゃっこうさん)に城砦の鎮護神として、近江より日吉大神を勧請したのが、その始まりとされる。
四代景家の養和元年(1181)木曽義仲の手勢手塚太郎光盛に攻められて落城、社殿も兵火にあったが、幸いにも片野の里人に守られ、杉ヶ平、元山王に奉遷(ほうせん)され産土(うぶすな)神として奉祀された。その後、歳月は流れて天正13年(1585)織田豊臣時代に秀吉の臣、金森長近が飛騨に入国し、国内統一を果して国守に封ぜられた。 そこで城山に築城するに当たり、金森氏が代々守護神として崇めていた日吉大神を慶長10年(1605)に至り、片野より現在の地へ奉遷して城の鎮守神とした。 『飛騨の神社』
末社に富士社・金刀比羅社・稲荷社・恵比寿社・産霊社、天満社・杉ヶ谷神明神社がある。
事務局 KN