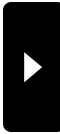スポンサーリンク
この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。
(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)
2020年07月28日
【地域の史跡20 松樹院歴代僧侶の墓】
【地域の史跡20 松樹院歴代僧侶の墓】

場所:山王公園 北 もみじ平
山王公園の山手の所に5基の墓がある。これらはかつての日枝神社の別当であった松樹院の住職の墓である。
一番右は六代祐智の墓で、「中興開基阿遮梨権大僧都法印祐智尊位、享和辛酉年三月十七日寂」とあり、一番大きい。
二番目は紋入りの笠石があり、初代良伝の墓。その左は二代良順の墓。八代頼応の墓。九代旭如の墓と続く。
松樹院は日枝神社の別当としてあった真言宗の寺院で、明治時代になって神仏分離令が出た時に廃寺とされた。
今でも、高山祭の時には、真言宗の国分寺の僧侶が来賓として呼ばれ、関係が続いている。
参考文献:『日枝神社史』
文責:KN
場所:山王公園 北 もみじ平
山王公園の山手の所に5基の墓がある。これらはかつての日枝神社の別当であった松樹院の住職の墓である。
一番右は六代祐智の墓で、「中興開基阿遮梨権大僧都法印祐智尊位、享和辛酉年三月十七日寂」とあり、一番大きい。
二番目は紋入りの笠石があり、初代良伝の墓。その左は二代良順の墓。八代頼応の墓。九代旭如の墓と続く。
松樹院は日枝神社の別当としてあった真言宗の寺院で、明治時代になって神仏分離令が出た時に廃寺とされた。
今でも、高山祭の時には、真言宗の国分寺の僧侶が来賓として呼ばれ、関係が続いている。
参考文献:『日枝神社史』
文責:KN
2020年07月25日
【地域の史跡19 富田豊彦碑】
【地域の史跡19 富田豊彦碑】

場所:山王公園 北 もみじ平
冨田豊彦(万延元年(1860)3,4~昭和15(1940)11.18)は、国学者・神職。高山生まれ。
道彦の子、礼彦の孫。幼名は銀之丞。
號は文坡。祖父の礼彦を始め佐々木弘綱、山崎弓雄などに国学や和歌、漢学などを学ぶ。
日枝神社社司、斐太中学教諭など歴任。荏名門の文台を継承し門人を指導。『岐阜県大野郡史』編纂委員の一人。
従七位勲八等瑞宝章。著書『飛騨古今詠歌人名録』『まゆみ園集』など。
碑文は
「宇祢比山吹支都多部来天長閑那里三千登勢知加幾松可是乃聲
(畝傍山吹きつたへ来て長閑なり三千年ちかき松風の聲)」
という国学系の人が好んだ万葉仮名的表現を草書体で記したもので、本人の81歳の揮毫によるものである。
彼の没後、昭和16年に門人有志によって建立された。
参考文献:『日枝神社史』『飛騨人名辞典』
文責:KN

場所:山王公園 北 もみじ平
冨田豊彦(万延元年(1860)3,4~昭和15(1940)11.18)は、国学者・神職。高山生まれ。
道彦の子、礼彦の孫。幼名は銀之丞。
號は文坡。祖父の礼彦を始め佐々木弘綱、山崎弓雄などに国学や和歌、漢学などを学ぶ。
日枝神社社司、斐太中学教諭など歴任。荏名門の文台を継承し門人を指導。『岐阜県大野郡史』編纂委員の一人。
従七位勲八等瑞宝章。著書『飛騨古今詠歌人名録』『まゆみ園集』など。
碑文は
「宇祢比山吹支都多部来天長閑那里三千登勢知加幾松可是乃聲
(畝傍山吹きつたへ来て長閑なり三千年ちかき松風の聲)」
という国学系の人が好んだ万葉仮名的表現を草書体で記したもので、本人の81歳の揮毫によるものである。
彼の没後、昭和16年に門人有志によって建立された。
参考文献:『日枝神社史』『飛騨人名辞典』
文責:KN
2020年07月24日
【地域の史跡18 川上哲太郎碑】
【地域の史跡18 川上哲太郎碑】
場所:山王公園 北 もみじ平
川上哲太郎氏(明治4(1871)9.27~昭和19(1944)1.25)は高山食品卸市場株式会社の初代社長で、号を文保と名乗り和歌をよくした。
昭和17年(1942)7月高山食品卸市場株式会社を創立し初代取締役社長。川上魚市場を改称した斐太食品工業(株)の社長も兼ねた。
冨田豊彦に和歌を学んだ。この石碑は、自然石に日枝神社宮司の森本榮樹が揮毫した歌碑となっている。
昭和35年6月25日に同社の三代目社長が建立した。
参考文献:『日枝神社史』『高山食品卸市場史』
文責:KN
場所:山王公園 北 もみじ平
川上哲太郎氏(明治4(1871)9.27~昭和19(1944)1.25)は高山食品卸市場株式会社の初代社長で、号を文保と名乗り和歌をよくした。
昭和17年(1942)7月高山食品卸市場株式会社を創立し初代取締役社長。川上魚市場を改称した斐太食品工業(株)の社長も兼ねた。
冨田豊彦に和歌を学んだ。この石碑は、自然石に日枝神社宮司の森本榮樹が揮毫した歌碑となっている。
昭和35年6月25日に同社の三代目社長が建立した。
参考文献:『日枝神社史』『高山食品卸市場史』
文責:KN
2020年07月21日
【地域の史跡17 包丁塚】
【地域の史跡17 包丁塚】

場所:山王公園 北 もみじ平
高椅神社が勧請されたときに一緒に造られた塚で、調理師の命ともいえる包丁を祀ってある。
年に一度、お祭が行われ、会員の中には包丁式を披露する方も見え、この場所での奉納が時々行われている。
包丁式とは、調理師が俎板前に置いて包丁と俎板着を用い一切手を触れる事なく鯛、鯉、真魚鱧などを調理する儀式で、
装束は烏帽子を被り、裃を着用し、調理人・立会人などにより執り行われる古式に則った日本料理の伝統を今に伝える
厳粛な儀式である。
参考文献:『日枝神社史』
文責:KN
場所:山王公園 北 もみじ平
高椅神社が勧請されたときに一緒に造られた塚で、調理師の命ともいえる包丁を祀ってある。
年に一度、お祭が行われ、会員の中には包丁式を披露する方も見え、この場所での奉納が時々行われている。
包丁式とは、調理師が俎板前に置いて包丁と俎板着を用い一切手を触れる事なく鯛、鯉、真魚鱧などを調理する儀式で、
装束は烏帽子を被り、裃を着用し、調理人・立会人などにより執り行われる古式に則った日本料理の伝統を今に伝える
厳粛な儀式である。
参考文献:『日枝神社史』
文責:KN
2020年07月18日
【地域の史跡15 高椅神社(たかはしじんじゃ)】
【地域の史跡15 高椅神社(たかはしじんじゃ)】

場所:山王公園 北 もみじ平
祭神:磐鹿六雁命(いわしかむかりのみこと)=料理の神様
山王公園北のもみじ平に鎮座する神社で、高山調理師会が創立三十五周年の記念事業として勧請し、昭和63年10月26日に鎮座債を行った。社殿は、日枝神社の旧天満神社の本殿を譲り受けた。旧天満神社は大正15年7月に新築奉遷されたもので、現在地の下の道脇にあった。高椅神社のご祭神は栃木県小山市字高椅の高椅神社である。祭神は磐鹿六雁命で、景光天皇の膳臣(かしわでのおみ)が宮中の料理を司る官職にあったことから料理の神様として崇敬を集めている。境内には包丁塚、石碑などがあり、松本市の調理師組合との記念植樹なども見られる。
参考文献:『日枝神社史』
文責:KN
場所:山王公園 北 もみじ平
祭神:磐鹿六雁命(いわしかむかりのみこと)=料理の神様
山王公園北のもみじ平に鎮座する神社で、高山調理師会が創立三十五周年の記念事業として勧請し、昭和63年10月26日に鎮座債を行った。社殿は、日枝神社の旧天満神社の本殿を譲り受けた。旧天満神社は大正15年7月に新築奉遷されたもので、現在地の下の道脇にあった。高椅神社のご祭神は栃木県小山市字高椅の高椅神社である。祭神は磐鹿六雁命で、景光天皇の膳臣(かしわでのおみ)が宮中の料理を司る官職にあったことから料理の神様として崇敬を集めている。境内には包丁塚、石碑などがあり、松本市の調理師組合との記念植樹なども見られる。
参考文献:『日枝神社史』
文責:KN
2020年07月12日
【地域の史跡14 筆塚】
【地域の史跡14 筆塚】

場所:日枝神社境内(本殿北側)
日枝神社の末社天満神社の前に「筆塚」がある。この塚はかつては現在の富士神社の場所にあったが、天満神社移転と共に現在地に移され、現在も筆供養が行われている。墓碑銘の揮毫は侯爵の前田利為前田利為(としなり 明治18年6月5日~昭和17年9月5日)侯爵。旧七日市半前田利昭の五男として生まれ、前田本家15代当主利嗣の養嗣子となり、旧加賀藩主前田本家第十六代当主となり陸軍大将。ボルネオ島沖で戦死。)が書いたもので、昭和4年7月に自然石で造られた。
参考文献:『日枝神社史』
文責:KN

場所:日枝神社境内(本殿北側)
日枝神社の末社天満神社の前に「筆塚」がある。この塚はかつては現在の富士神社の場所にあったが、天満神社移転と共に現在地に移され、現在も筆供養が行われている。墓碑銘の揮毫は侯爵の前田利為前田利為(としなり 明治18年6月5日~昭和17年9月5日)侯爵。旧七日市半前田利昭の五男として生まれ、前田本家15代当主利嗣の養嗣子となり、旧加賀藩主前田本家第十六代当主となり陸軍大将。ボルネオ島沖で戦死。)が書いたもので、昭和4年7月に自然石で造られた。
参考文献:『日枝神社史』
文責:KN
2020年07月09日
【地域の史跡13 堀左明の碑】
【地域の史跡13 堀左明の碑】

場所:日枝神社境内 一の鳥居参道東側
堀左明は江戸時代の能書家で、高山の人。門人が多く大阪で活躍した人のようである。
堀左明(ほり・さめい)
享保6年(1769)~天保7(1836)7・29
俳人・能書家。高山の人。通称は六蔵。名を文篤。俳句と生花を好み、能書で門人が多かった。享年66歳。(飛騨人物考、斐山語草)『飛騨人物事典』
石碑には次のように書かれている。「左明堀翁之碑
翁諱文篤堀氏称六蔵法謚義章左明其號飛 騨高山人萬人風流潚酒不屑俗務平生好俳
諧挿花以自娯馬而特善書受業者頗多天保 七年丙申七月廿九日病没年六十有六項者
門人某等謀立喝於松樹院来請銘上曰
生能自楽 没為人慕 名傳永世 昂斯松樹
嘉永四年辛亥春正月 浪華 七十一老人菠崎弼撰幷書」
「司事 飯島喜兵衛由訓 石匠 大坂 飯田新三郎昌應」
参考文献:『飛騨人物考』『斐山語草』『飛騨人物事典』『日枝神社史』
文責:KN

場所:日枝神社境内 一の鳥居参道東側
堀左明は江戸時代の能書家で、高山の人。門人が多く大阪で活躍した人のようである。
堀左明(ほり・さめい)
享保6年(1769)~天保7(1836)7・29
俳人・能書家。高山の人。通称は六蔵。名を文篤。俳句と生花を好み、能書で門人が多かった。享年66歳。(飛騨人物考、斐山語草)『飛騨人物事典』
石碑には次のように書かれている。「左明堀翁之碑
翁諱文篤堀氏称六蔵法謚義章左明其號飛 騨高山人萬人風流潚酒不屑俗務平生好俳
諧挿花以自娯馬而特善書受業者頗多天保 七年丙申七月廿九日病没年六十有六項者
門人某等謀立喝於松樹院来請銘上曰
生能自楽 没為人慕 名傳永世 昂斯松樹
嘉永四年辛亥春正月 浪華 七十一老人菠崎弼撰幷書」
「司事 飯島喜兵衛由訓 石匠 大坂 飯田新三郎昌應」
参考文献:『飛騨人物考』『斐山語草』『飛騨人物事典』『日枝神社史』
文責:KN
2020年07月06日
【地域の史跡12 曽我秀文の住居地】
【地域の史跡12 曽我秀文の住居地】



場所;石浦町1丁目(字坂口)
石浦町1丁目にある。室町時代に日本に渡来した明国人の曽我秀文(生年不詳~享禄3(1530)8.25享年79)が住んだ場所。
曽我秀文は初め越前に住み、白川郷を経て飛騨(石浦村坂口)に移り住んだ。現在も曽我秀文が住居としていた場所が石浦町に残っており、その土地の上に建物が建てられ、遺跡が残っている。
秀文は医術に長け、農業にも詳しく里人の尊敬を集めたため、祭神として祀られたという。
昭和57年に中国大使館の公使が来高した際にこの地を参詣し、感激されたという逸話が残っている。
参考文献:『高山市史』『飛騨人物辞典』
文責:KN
場所;石浦町1丁目(字坂口)
石浦町1丁目にある。室町時代に日本に渡来した明国人の曽我秀文(生年不詳~享禄3(1530)8.25享年79)が住んだ場所。
曽我秀文は初め越前に住み、白川郷を経て飛騨(石浦村坂口)に移り住んだ。現在も曽我秀文が住居としていた場所が石浦町に残っており、その土地の上に建物が建てられ、遺跡が残っている。
秀文は医術に長け、農業にも詳しく里人の尊敬を集めたため、祭神として祀られたという。
昭和57年に中国大使館の公使が来高した際にこの地を参詣し、感激されたという逸話が残っている。
参考文献:『高山市史』『飛騨人物辞典』
文責:KN
2020年07月03日
【地域の史跡11 曽我秀文の墓】
【地域の史跡11 曽我秀文の墓】
場所:高山市石浦町1丁目

室町時代に日本に渡来した明国人の曽我秀文(生年不詳~享禄3(1530)8.25享年79)の墓。
曽我秀文は初め越前に住み、白川郷を経て飛騨(石浦村坂口)に移り住んだ。現在も曽我秀文が住居としていた場所が石浦町に残っており、その土地の上に建物が建てられ、遺跡が残っている。
秀文は医術に長け、農業にも詳しく里人の尊敬を集めたため、祭神として祀られたという曽我神社が現存し、片野町の秀文顕彰会の皆さんによって護持されている。
昭和57年に中国大使館の公使が来高した際にこの地を参詣し、感激されたという逸話が残っている。
参考文献:『高山市史』『飛騨人物事典』
文責:KN
場所:高山市石浦町1丁目
室町時代に日本に渡来した明国人の曽我秀文(生年不詳~享禄3(1530)8.25享年79)の墓。
曽我秀文は初め越前に住み、白川郷を経て飛騨(石浦村坂口)に移り住んだ。現在も曽我秀文が住居としていた場所が石浦町に残っており、その土地の上に建物が建てられ、遺跡が残っている。
秀文は医術に長け、農業にも詳しく里人の尊敬を集めたため、祭神として祀られたという曽我神社が現存し、片野町の秀文顕彰会の皆さんによって護持されている。
昭和57年に中国大使館の公使が来高した際にこの地を参詣し、感激されたという逸話が残っている。
参考文献:『高山市史』『飛騨人物事典』
文責:KN
2020年06月29日
【地域の史跡10 曽我神社】
【地域の史跡10 曽我神社】

場所:高山市片野町1丁目地内
祭神:曽我秀文
片野町1丁目の山腹にあり、飛騨地区では珍しい神社。祭神は室町時代に日本に渡来した明国人の曽我秀文(生年不詳~享禄3(1530)8.25享年79)を祀っている。曽我秀文は初め越前に住み、白川郷を経て飛騨(石浦村坂口)に移り住んだ。現在も曽我秀文が住居としていた場所が石浦町に残っており、その土地の上に建物が建てられ、遺跡が残っている。秀文は医術に長け、農業にも詳しく里人の尊敬を集めたため、祭神として祀られたという。昭和57年に中国大使館の公使が来高した際にこの地を参詣し、感激されたという逸話が残っている。
参考文献:『高山市史』『飛騨人物事典』
文責:KN
場所:高山市片野町1丁目地内
祭神:曽我秀文
片野町1丁目の山腹にあり、飛騨地区では珍しい神社。祭神は室町時代に日本に渡来した明国人の曽我秀文(生年不詳~享禄3(1530)8.25享年79)を祀っている。曽我秀文は初め越前に住み、白川郷を経て飛騨(石浦村坂口)に移り住んだ。現在も曽我秀文が住居としていた場所が石浦町に残っており、その土地の上に建物が建てられ、遺跡が残っている。秀文は医術に長け、農業にも詳しく里人の尊敬を集めたため、祭神として祀られたという。昭和57年に中国大使館の公使が来高した際にこの地を参詣し、感激されたという逸話が残っている。
参考文献:『高山市史』『飛騨人物事典』
文責:KN